2014年09月26日
荻原くんと萩原くん

[日常] 萩野と荻野の区別が付きにくい。
先日も母がテレビを見ながら、泳ぐ萩野(はぎの)選手に対して「おぎのー!!いけ、おぎのー!!」と、絶叫しながら応援していたほど。絶叫してるけど間違ってるという。
ややこしいのは萩野と荻野の対だけでなく、萩原と荻原の組もあるからだと思う。
僕は一応、間違えないための目印を持っている。小学生のときに、クラスにいた小太りの荻原(おぎわら)くんという友達がいて、その子から手紙をもらったときに、自画像が書かれていたことがあった。
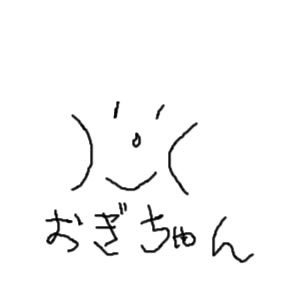
こんな絵。自分でもふっくらしていることを自覚していたようだ。
この荻原くんの太った自画像がヒントになり、そのふっくらした頬にけものへんを重ねることによって区別を付けることに成功したのだ。
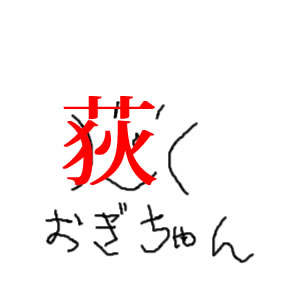
荻原くんの頬に重なる文字が、”荻”だ!
これは荻原君との歴史がある僕にしか通用しない区別法なので、この日記は一体何なんだというものにはなったが、たぶん世間の人も自分なりの区別の仕方があるのだろう。
2014年09月21日
演劇と支配

[日常] とある演劇ニュース。
二ページ目いらんやろ。
--------
暴力をふるう指導者というのはどこにでもいると思うけど、演出家や監督の場合、体育教師などと違って「言葉を持っている」という点で、動機の質が違う。
つまり言葉で指導することも技術的には可能だが、あえて暴力という手段をとっているのだろう。おそらくそれは演劇(劇場)的な効果を狙っていて、暴力空間を共有させることによって支配関係を公に構築する意図があるのだ(それも間違っている方法だと思うが)。性的な興奮を満たすための役割もあって、一石二鳥というわけである。
やっかいなことに、役者と演出家という立場はそういうことが最もやりやすい環境にある。宗教において教祖と信者の関係でも起こりやすいのは周知のことだが。
基本的に演出家や監督という生き物は、大嘘つきのド変態でなければ務まらない仕事である。ただ、それを作品以外のところでは理性で押し込めて生きていくべきなのだが、たまにその変態性をあえて包み隠すことなく「自分はちょっと社会からはみ出てしまう、やんちゃな芸術家なんだ」とふるまう人たちがいる。
そういう人たちの存在が記事の二ページ目にある「演劇人って難儀な生き物」という一般評価に繋がるのだろう。
2014年09月20日
動かされている

[日常] すっかり寒くなってきました。
大阪には半袖短パンしか置いてないので寒いのだけど、かといって家の人が着ている長袖やジーンズなどはサイズが違うし(妙に大きい)、なんだかいろいろ古いし着る気がおきないのです。
ところが「長袖いる?」「いらない」「長袖いるやろ?」「いらないってば」「長袖おいといたから」「!」と、押し切られる実家あるある。すべてが結論ありきです。
--------
大阪では基本的に車移動なのだけれど。
最近の車は(というかうちの車は)、アクセルを踏んだり、ハンドル操作をするときに、思い通りに動かしているように見えて、コンピューターが間にガッツリ入って制御し直されている気がする。アクセルを適当に踏んでも適切なスピードを保っているし、ハンドルを適当に傾けてもきっちり曲がっていくから。
なんというか、表現は難しいけど、ハンドルの向こうにもう一人小さいプロの運転手が入ってて、「こういうことかい?」と運転し直されてる感じ。いや、もうそんなんだったら表に出てきて運転してくれれば。
やがて、運転席にはブレーキしか無くなる時代も来るでしょう。
2014年09月19日
動かぬ台車

[日常] 重い台車を転がすとき、最初にものすごく力がいるように、実生活で何か新しいことを始めるときも、最初にものすごく力がいるし、なかなか思い通りに転がってくれないことがある。
自身の体験でいえば、受験のとき、バイトを始めたとき、会社に入ったとき、そして自営業になったとき、人生の節々で同じことを感じて生きてきた。いわゆる「壁」と表現されることもあるけど、僕の場合は「台車」のイメージに近い。
最初はどんなに力強く押してもビクともしない。ところが少し転がりはじめると(決して楽ではないが)、スーッと転がり続ける不思議がある。「あれ、力入れなくても動くの?」という不思議。台車が軽くなったわけではないから、押し方のコツを覚えたのだろうが、実感がない。そしてまた、油断した頃に大きな石にぶつかって止まるのだ。
あまりにも要領が悪いために、動かない台車に出会う数も多く、この歳になると「はいはい、いつもの動かないやつね」と焦らなくなった。いや、焦れよという気持ちもあるのだけど、こればかりは、自分というやつにそこまで期待してないんですな。諦めもしないけど、期待もしない。
期待してないから、大した失望もないんです。
2014年09月17日
おっさんがおっさんに

[日常] 毎朝、実家の犬ドッグを連れて散歩しています。

犬ドッグ
彼はいつも外でウンコすることを日課にしているらしく、しかも本人的には場所が決まっているようで、そのスポットに近づくと足が早まります。もう出るし、もう出るし、みたいなことなんでしょうか。
この前、散歩に出てすぐに僕のほうがお腹が痛くなって自宅に引き返そうとしたところ、犬ドッグが「いや、そういうことなら、ここでするし!」と慌てて道路の真ん中でウンコしだしたのは申し訳なかったです。多くを語らないだけに、その行動の節々に哀愁を感じます。
この犬ドッグは人間に換算すると御年34歳だそうで(その根拠も怪しいですが)、ほぼ同い年。34歳のおっさんが35歳のおっさんに抱きついてベロベロに舐めるという地獄絵図、人に見せられるものではありません。
2014年09月16日
自己満足

[日常] in大阪・別宅です。
一階の掘りごたつで作業をするのはどうも腰が痛くて集中できんなあということで、十五年ぶりに二階の自分の机を片付けて仕事場をしつらえました。中学生から高校卒業まで自分が使っていた机です。
父親のギターだのプリンタなどが乗せられていたのですが、それらを降ろして、十五年ぶりに電気スタンドをスイッチオン。
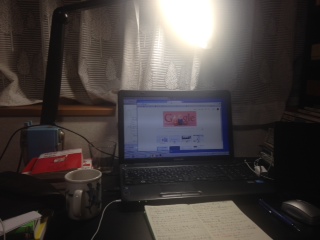
つきました!
蛍光灯自身も「え!?」と思ったことでしょう。かつて慣れ親しんだ机だけあって使いやすく高さもちょうどいいのですが、どうも受験勉強とかで追い込まれた記憶が蘇ってきてダメですね。当時、高校生だった僕も「こんなつらい思いしてまで、将来の自分はどうなってるんだろう?」と思ったことがあります。アンジェラアキの歌みたいなやつです。
昔の自分に声を掛けられるなら「その努力は自己満足だぜ」と語りかけたいです。
2014年09月15日
シンプル

[日常] 映画「舞妓はレディ」を見ました。
周防監督の変態性が随所に良く出ている素晴らしい映画でした。シンプルでごまかしようのない、真っ直ぐな(ように感じる)演出に、とてつもない技術を感じます。
ジャンルは全然違うけど、周富徳がホテルの総料理長の試験のときに、制限時間の終了間際まで何もせず、最後の5分でシンプルなチャーハンを作って勝ったとか、そういう美学に近いと思います。
似たようなものに「あえてシンプルにした」というようなものがあるけど(無印良品のような)、あれはシンプルを身に纏った付け足しの演出です。世の中には「無駄なんで外しました」というシンプルと、「このほうがオシャレでっしゃろ」というシンプルがある。そのシンプルたる所以が”機能”から生まれているか、”デザイン”から生まれているか、の違いですね。
飾りを取っ払って無駄を削いでいくと、残るものは非常に小さくなるものです。たまに何も残らないことがあって、「全部がいらないものだった」と気づくこともあるくらい。付け足す演出と取り除く演出。そのバランスが絶妙なのが今回の映画でした。
2014年09月13日
ヤーさん

[日常] 先日、母が知人方からお米をいただいたらしい。
そのお礼としてハムを贈ったらしいのだが、そのお返しにまたご丁寧な手紙をもらい、「何を返せばいいだろうか」と頭を悩ませている。いや、その手紙はハムのお返しだし、ハムは米のお返しなんだよね? もういいんじゃないの?
この先、一体何に収束していくのだろう。一年後には泥団子でも投げ合ったりして。
--------
EXILEグループの組織構造というか、裾野の広げ方はヤーさんのそれと似ていると思うのだけど、それは別に悪口ではなくて「絆」とか「夢」で人を繋ぐには理にかなった作り方なのかもしれない。時代劇とか見てても昔の組織って全部そうだし。
関係ないけど、錦織選手が決勝進出を果たしたときのニュースコメントに、一般の方が「夢の第一章完結にむけて頑張って下さい!」と書き込んでいて、いや、こんなところにもEXILEの息が、と思った。
「フィジカルがさあ」とか言うサッカーファンとかも、かなり流行に毒されてるよね。君、10年前はそんな単語使ってなかったでしょっていう。
2014年09月11日
シムシティの感覚

生活保護費29万円「生活苦しい」
この記事を読んだ多くの人は「いや、贅沢じゃないか?」という印象を抱くらしい。そのような印象操作のある記事だ。確かに、一般的な感覚に照らし合わせればそうだろうが、それは広い意味で「健全な人」の考え方であって、それは同じく健全な人にしか通用しない論理だと思う。
「健全な人」は、月に10万や15万でも節約して創意工夫で頑張れるだろうが(劇団員の鈴木さんとか)、保護を受けている人たちは単なる金銭的な貧困とは一味違う。「ギリギリ」の状態を与えればさらに破綻しやすくなり、やがて追いつめられ、社会から完全にドロップアウト(自殺や犯罪に手を染めるなど)する結果に直結する。ドロップアウトした人が溢れかえれば、治安は悪化するだけだ。
少なくともシムシティではそうなります。
受給者を「健全な人」に戻していくような仕組みが無いかぎりは、現行のような、ある程度十分な金額を与えて「これでひとつ、大人しくしてください」とフタをするしかなく、それはそれで残酷な制度なのである。
2014年09月10日
誤りチェック体制

[日常] 巷で話題の、「お値段以上」ではなかった広告。

中学受験とかで出題されそう。
最近のネットニュースの記事もそうだけど、パッと見ればわかるようなミスもそのままリリースされちゃっているのは、チェックする人がいないのだろうか。ニトリには理系の人がいなかったのかな。いや、そんな問題でもないような。その点、やっぱり新聞はすごい。
海外のホテルとかで無茶苦茶な日本語の注意書きを見ることがあるけど、僻地でもないんだからちゃんと日本人にチェックさせればいいのに、してないんだろうな。全然分かってないのに、周りから「あの人は日本語できるから」と持ち上げられて断り切れずにやることになったか、翻訳ツールで適当に済ませたか。
たまに、「何を見て書き写したの?」と言いたくなるやつあるよね。
<<前のページ
次のページ>>
|