2006年07月29日
稽古

次回公演『マンモス』の稽古が今週から始まりました。代沢の稽古場を覗いてきました。

まだ台本を使っての稽古はしてなくて、今日はエチュードをしていました。簡単な設定だけ与えられて、即興で芝居を作るというもの。
一つ目は不動産屋と住人とのやり取り、二つ目は小学校の同窓会という設定でした。

午前中には横浜の相鉄線沿い某所で、チラシの撮影も行われました。写真を見せてもらいましたが、なかなか良いものが撮れていました。
8月上旬にはお目にかかれます。
(制作・菊池)
08_マンモス
日時: 21:16
| パーマリンク
2006年07月26日
〔自由研究〕ラムネ

夏と言えばラムネです。
今日、制作の仕事で行ったとある劇場で、ついでにお芝居を観ました。ラムネにまつわる芝居で、終演後に受付でラムネを配ってた(飲料メーカーの協賛のようです)ので久し振りに飲みました。

幼い頃、縁日の日に、ラムネのあの、ビー玉の仕組みを父に聞いたのですが、理解できませんでした。
25歳になった今、多分理解できるので、自由研究しました。
ラムネ−Wikipedia
この瓶は、上から5分の2ほどの位置にくびれが設けられており、口とくびれの間にラムネ玉(A玉)と呼ばれるガラス球が封入されている。この瓶に飲料を充てんし、間髪をいれずに上下をひっくり返すと、内部の炭酸ガスの圧力でラムネ玉が口部のゴムパッキンに押し付けられ、瓶が密閉される。中身を飲む際は、ラムネ玉を瓶内に押し込むことにより内圧を逃がすことで開栓する。このときのため専用の「ラムネ開け」が用意されている。
なるほど。今度は理解できました。封がしやすくて、開けやすい。発明者は上手いこと考えたものです。
ガラス瓶に王冠で栓をする技術の普及や、缶飲料の登場でシェアは小さくなっている。それに伴い専用瓶のメーカーも少なくなり、2006年現在生産はされていない。言い換えればほぼ100%リユースされていることになる。
自分も息子に同じことを教えたいので、ラムネには絶滅しないでもらいたいものです。
(制作・菊池)
2006年07月22日
〔自由研究〕セミの命

夏と言えばセミですが、セミが地下では何年も生きるのに、地上に出てから1週間しか生きられないのは、ちょっと可哀想な感じがしますね。これからだって時期に。
それは人間基準なので余計なお世話ですが、なぜセミの一生はそんなにアンバランスなんでしょう。
神様からのメッセージ?世の中は無常なんですよ、っていう。自由研究しました。

セミ−Wikipedia
載ってませんでした。残念です。
せめて何か自由研究っぽいこと無いかと探してみたら、豆知識がありました。
明治維新の時、日本にやってきたヨーロッパ人はイタリアや南仏などの地中海沿岸地域出身者を除くとセミを知らないものが多く、「なぜ木が鳴くのか」と尋ねたものもいたという。現在でも、日本のドラマを欧米に出すとき、夏の場面ではセミの声を消して送るという。日本ではいかにも暑い盛りのBGMと感じられるが、あちらでは妙なノイズが乗っていると思われる場合が多いという。
この自由研究遊び、あわよくば流行らないでしょうかね。ブロガーの間とかで。自分の知識じゃなくて、他人の知識を披露するのがミソなので、楽できると思います。
乗ってくれるブロガーがいたら、記事をトラックバックしてください。
(制作・菊池)
2006年07月18日
全体会議

久々にとくお組の話題です。
日曜に、久々にとくお組全体で集まって、会計報告や次回公演『マンモス』の打ち合わせなどをしました。
制作がまとめた会計報告に目を通しながら、お金のことをあれやこれやと話しました。
とくお組の経営は、あっぷあっぷと言う程ではありませんが、課題も少なからずあるので、会議は皆「うーむ」という雰囲気です。
『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』でも読んでみましょうか。

『マンモス』の公演情報は、来月上旬頃ホームページにアップ予定です。
ホームページのオンラインショップは、現在、外部のプログラマの方が設計中です。
こちらも同じ頃に開設できると思うので、どうぞよろしくお願いします。
(制作・菊池)
2006年07月15日
〔自由研究〕もんたよしのり

『ギャランドゥ』を作詞・作曲した、もんたよしのりってどういう人なんでしょう。聞いたことぐらいはあるけど、この機会に詳しく知りたい。「もんた」って本名なのか知りたい。自由研究しました。

もんたよしのり−Wikipedia
経歴
・1971年にソロ歌手としてデビュー。
・1980年に「もんた&ブラザーズ」として「ダンシング・オールナイト」をリリース。大ヒットとなり、同年のNHK・紅白歌合戦に出場した。
・また、2004年4月15日にナインティナイン(岡村隆史、矢部浩之ともに)がパーソナリティをつとめるニッポン放送系ナインティナインのオールナイトニッポン(木曜25:00-27:00)にゲスト出演した際に「ハナクソやで」という口癖があることが発覚した。
この情報量の少なさはどういうことでしょう。
「紅白出場」と「『ハナクソやで』という口癖の発覚」が「また、」で同列に接続されてるのも可愛そうです。
最近はマウンテンバイクで山を走っている。
なんかネタにされてる感がありますね。
ついでに、もんたよしのりの公式ページのセンスも、一見の価値ありです。
(制作・菊池)
2006年07月13日
〔自由研究〕ギャランドゥ

とくお組の表立った活動の情報が無い時期のため、関係無い話題が続くブログです。
今はオンライン百科事典のWikipediaで自由研究をする記事を書いてます。
さて、夏と言えば薄着、薄着といえばギャランドゥですが、ギャランドゥって何語なんだろう。ギャランティとか、ギャラクシーとかと似たカッコいい語感で、「ヘソの周りの毛」を表すにはもったいないのではないか。役不足ではないか。そう思って、ちょっと前に調べました。
ギャランドゥ−Wikipedia
ギャランドゥ(ぎゃらんどぅ)は、もんたよしのりが作詞・作曲(大谷和夫が編曲)し、1983年に西城秀樹が歌ってヒットした楽曲である。
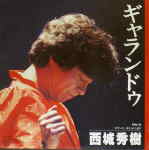
びっくり。知りませんでした。上の世代の人には常識なのでしょうか。
ギャランドゥという言葉は、「gal un do」あるいは「gal and do」から来た造語で、魅惑的な女性の意味などと言われることがあり、西城自身もそのようなコメントをすることがある。しかし、もんた自身は、意味は後付けであり、本来は意味はないとコメントしている。作曲をする際にデタラメな英語で歌いながら作ることがあり、「ギャランドゥ」という語はその時に生まれたデタラメな語であり、語感がいいのでそのまま採用されたとのことである。
2人で摺り合わせができてませんね。
ギャランドゥという語は以上のような経緯で生まれた語であるが、転用され、ヘソの周りに生えている体毛あるいはそれが濃い状態を指す言葉として使われることが多い。これは、(ギャランドゥがヒットしていた当時)西城が水着姿になると腹部に生えている体毛がパンツの中にまで続いている状態であり、それがやたら目立っていたことに由来する。このような意味で初めて使用したのは松任谷由実あるいはタモリであると言われているが、詳細は不明である。
なるほど。もんたよしのりも、自分の作った言葉が「ヘソの周りの毛」という意味で生き続けるなんてどういう心境なんでしょうね。
(制作・菊池)
2006年07月11日
〔自由研究〕マッコウクジラ

夏と言えば海で、海と言えばマッコウクジラです。
前にNHKの番組で見たのですが、マッコウクジラはエサを獲るために、最大で3000メートルの深さまで潜るらしいです。(海女さんは30メートル。)
海面で空気を吸って、潜って、エサ食べて、海面に上がる、というのを1時間サイクルで繰り返すとのこと。

潜る姿はこんな感じです。ほとんど鉛直です。
何でそんなにスマートに潜ったり、逆に浮かんだりできるのか、不思議に思ってました。
マッコウクジラの密度は海水より大きいのか小さいのか。
そこでWikipediaで自由研究です。
マッコウクジラ-Wikipedia
ありました。
説でしかありませんが、「鯨蝋」という節に書いてあります。
鯨蝋とは頭部から採取される白濁色の物質(脳油)の別名である。(中略)鯨蝋(脳油)は、マッコウクジラの体温下では液状であるが、約25℃で凝固する事が知られている。鯨類学者クラークはこの性質に着目し、潜水の際には鼻から海水を吸い込み冷やすことで脳油を固化させ比重を高め、浮上の際には海水を吐き出し血液を流し温めることで液化させ比重を小さくすることで急速な潜水および浮上を可能にしているという説を唱えている。
すごい原理なんですね。
どういう進化でこんな便利な体になったんでしょう。
人間の技術にも応用できそうです。
Wikipediaには、「マッコウ」の語源や、マッコウクジラと日本の開国との関わりなども書いてあって、思わぬ収穫がありました。
(制作・菊池)
自由研究

もうすっかり夏で、夏といえば自由研究です。
小学生の頃、自由研究で色々調べたりしましたが、インターネットの普及した今なら、もう相当な数の自由研究ができるのではないでしょうか。

最近はWikipediaという百科事典のようなサイトが台頭してきて、重宝しています。
項目によってはトリビア的なことも載っていて、ZARDを調べたら新しい発見があったように、へぇと思うことが少なくありません。
そこで、長いこと疑問に思っていたことをWikipediaで調べて、ブログに載せるというシリーズを、ちょっと他力本願な企画ですが明日からやってみようかなと思います。
(制作・菊池)
2006年07月07日
講演会

徳尾の大人計画フェスティバル参加に感化されて、桜美林大学での松尾スズキさんの講演会に行ってきました。

学生主催のイベントだったので、話のメインは、福岡での学生時代(演劇研究会に入ってたらしいです)から、上京、会社勤務、ニート生活、大人計画旗揚げまで。
大物の冴えない時代のエピソードを聞くのが好きなので、楽しめました。
演劇研究会(部員3人)での初めての公演は、教室を借りての公演で、照明を吊ることができないばかりか、蛍光灯を点けたり消したりする係もいなかったようです。
暗転後は、役者が自分で蛍光灯のスイッチを入れてから演技を始めるそうです。
蛍光灯のスイッチを押してから明かりが点くよりも早く、明転後の立ち位置に行かねばならず苦労したとのことでした。
大人計画の旗揚げ公演は、とくお組の次回公演でも使う、新宿のタイニイアリス(移転前)だったとのこと。
劇場を無料で借りる代わりに、他の劇団の公演が終わった後の夜10時から、客席の桟敷部分を使ってやったそうです。
楽屋も借りられず、開演前の役者は衣装を着て、劇場の下のゲームセンターで待機したそう。
シアターコクーンの公演ですらチケット入手困難な今からは、想像がつきません。
そういう、規模の変化を楽しむのも、劇団の楽しみ方の一つなのかもなと思いました。
(制作・菊池)
2006年07月03日
Mtgって何ですか?

前の記事の続きです。

−平均的な一日のスケジュールを教えてください。
「朝会社着いたら、まずメールチェックですね。
その後知り合いのホームページ見たり、mixi見たり。
昼食後は打ち合わせとかが多いです。」
−打ち合わせですか。そういえば、たまに見かける「Mtg」っていうのはミーティングのことですか?
「そうです。手帳に書くときとか、会議って書くより楽ですからね。
それはいいとして、社会人って聞きなれない横文字をよく使う。
決定のことをデシジョンとか。ドキュメントとかね。文書でいいのに。
あとは、ペンディング、マージ、アウトプット、タスクとか良く使いますね。
感化されて日常で使う人もいます。」
−なるほど。慣れるの大変そうですね。

−今後のキャリアプランを教えてください。
「ITコンサルの経験を積んで、3年後に独立を考えています。
これからはITの時代だと踏んでます。」
−ITの時代って…数年遅いじゃないですか。
学生のときと社会人になってからと、違いはありますか?
「学生は大学に行ける。社会人は会社に行かなくちゃいけない。」
−これから就活をする学生にメッセージをお願いします。
「景気回復で採用枠増えて良かったじゃんか。(ここでなぜか『じゃんか』をそのままの表記にするよう要求が。)
あ、あと会社入ってから知ったんだけど、ちょっと上の世代になると、
もう『就活』って言葉が通じないんですね。『就職活動』って言わなきゃ通じない。」
−最後に、梅雨に聴きたいJポップを教えてください。
「MISIAの『つつみ込むように…』です。」
−本日はありがとうございました。

社会人についてよく分かりましたね。
今回話を伺った方は、とても気さくな方でした。
(制作・菊池)
|